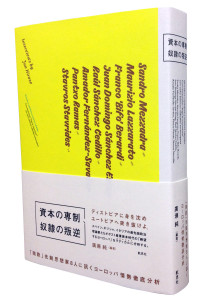オペライズモ、主観性、階級構成(第1部)
Intervista a Gigi Roggero. Operaismo, soggettività e composizione di classe (1) 廣瀬 純
 ジジ・ロッジェーロ(Gigi Roggero)は1973年生まれ、ボローニャ在住の研究者。住宅や学内空間の占拠などを行ってきたことで知られるボローニャ大学学生を中心としたグループHoboのメンバー、政治と理論についてのインタネットサイトCommonwareを運営。共著に、オペライズモを歴史的かつ理論的に論じたFuturo anteriore. Dai «Quaderni rossi» ai movimenti globali: ricchezze e limiti dell’operaismo italiano (2002)、オペライスタたちへのインタヴュー集Gli operaisti (2005)など(共にDeriveApprodi刊)。単著に、労働の認知化の観点から欧州および米国での大学の変容を論じたLa produzione del sapere vivo. Crisi dell’università e trasformazione del lavoro tra le due sponde dell’Atlantico (Ombre Corte, 2009)、同書英語版The Production of Living Knowledge. The Crisis of the University and Transformation of Labor in Europe and North America (Temple University Press, 2011)、コモンをめぐる今日的問いのなかでレーニンを再読するLa misteriosa curva della retta di Lenin. Per una critica dello sviluppo del capitalismo oltre i «beni comuni» (La Casa Usher, 2010)など。
ジジ・ロッジェーロ(Gigi Roggero)は1973年生まれ、ボローニャ在住の研究者。住宅や学内空間の占拠などを行ってきたことで知られるボローニャ大学学生を中心としたグループHoboのメンバー、政治と理論についてのインタネットサイトCommonwareを運営。共著に、オペライズモを歴史的かつ理論的に論じたFuturo anteriore. Dai «Quaderni rossi» ai movimenti globali: ricchezze e limiti dell’operaismo italiano (2002)、オペライスタたちへのインタヴュー集Gli operaisti (2005)など(共にDeriveApprodi刊)。単著に、労働の認知化の観点から欧州および米国での大学の変容を論じたLa produzione del sapere vivo. Crisi dell’università e trasformazione del lavoro tra le due sponde dell’Atlantico (Ombre Corte, 2009)、同書英語版The Production of Living Knowledge. The Crisis of the University and Transformation of Labor in Europe and North America (Temple University Press, 2011)、コモンをめぐる今日的問いのなかでレーニンを再読するLa misteriosa curva della retta di Lenin. Per una critica dello sviluppo del capitalismo oltre i «beni comuni» (La Casa Usher, 2010)など。以下は2016年3月25日に、ボローニャでロッジェーロらが共同運営するインフォショップGatewayにてイタリア語で行ったインタヴューのその第一部である。日本語への翻訳はインタヴュワーである廣瀬自身が行った。

今回のインタヴューでは、君が今年1月に発表した新著『ミリタンシーを讃える――主観性と階級構成とについての覚書』(Elogio della militanza. Note su soggettività e composizione di classe, DeriveApprodi, 2016)について話をききたいと思っている。タイトルには3つのキーワードが含まれている。「ミリタンシー」「階級構成」そして「主観性」。今日、これらのタームで政治を論じる必要があるのだとすれば、その必要性はどこから来るのか。「思考はつねに対立から生まれる。思考するとは何かに同意することではなく、何かに異論を唱えることだ」と君は書いている。今回の本は何に異論を唱えるものなのか。上記の3つのキーワードについての説明もまじえながら、この点について話してもらえると嬉しい。
今回の本の副題「主観性と階級構成についての覚書」はぼく自身が提案したものだが、メインタイトル「ミリタンシーを讃える」は出版社からの提案で、本の内容を鋭く言い当てたものだと思っている。というのも、この本はミリタントによって書かれ、ミリタントに読まれるべきものとして構想されているからだ。
副題に含まれている概念「主観性」「階級構成」についてまず説明したい。「階級構成」という概念は、1950年代末から1960年代にかけてイタリアで展開された政治運動であるオペライズモによって創り出されたものだ。より厳密には、ロマーノ・アルクァーティ(Romano Alquati)が創造したと言ってよい。アルクァーティはオペライズモの中心人物のひとりで、トリーノのフィアット社やオリヴェッティ社の工場で労働者たちとの「コンリチェールカ」(共同調査)を実践するなかでこの概念を創り出した。彼が当時「クァデールニ・ロッシ」や「クラッセ・オペラーイオ」といった雑誌に寄稿したテクストは七〇年代に入ってから一冊の本にまとめられている(Sulla Fiat e altri scritti, Feltrinelli, 1975)。アルクァーティの仕事を無視してオペライズモを語ることはできない。
「階級構成」概念は「資本の有機的構成」というマルクスの概念を参照したものだ。マルクスにおいて問題となっていたのは固定資本と変動資本とのあいだの関係だったが、「階級構成」概念はこのマルクスの概念を主観化するものだったと言える。オペライズモが問題にした関係は階級の「技術的構成」と「政治的構成」とのあいだのそれだった。図式的に言えば、階級の技術的構成とは、資本による労働力の節合、労働者と機械との関係のことであり、政治的構成とは、傾向的に自律的な政治主体としての労働者の自己形成のことだ。
技術的構成と政治的構成とに加えてアルクァーティは「再構成」という第三の要素を重視した。「再構成」というのは、資本による労働力の節合のその切断のことであり、新たな自律的主体の形成のことだ。再構成は、すでにあった状態に戻ること、資本によって破壊された階級のその「本来の姿」に戻るといったことではなく、生成状態にある力能がひとつのかたちをなすということだ。階級の政治的構成は、敵対的革命主体としてではなく、むしろ、たんに、階級の政治的表現として、どんな方向にも進み得る両義性を孕んだものとして理解すべきだ。オペライズモは、疎外なき原初状態に戻ろうと呼びかけるヒューマニズムでも、「労働者としての労働者」といったものへの盲信でもなかった。オペライスタたちは「大衆労働者」(テイラーシステムの生産ラインにおいて労働に従事する労働者)と彼らの呼ぶ特定の階級構成を同定した上で、たんに資本に抗するだけでなくおのれ自身にも抗する新たな主体の構築のその可能性を問題にしたのだ。オペライスタたちにとって労働者階級は称揚の対象ではまるでなく、搾取の条件であり、したがって破壊すべき対象だった。問題は階級がおのれ自身に抗するということだった。オペライズモでは、したがって、労働もまた称揚の対象ではない。オペライズモでは「疎外」が「外部性」と読み替えられ、労働の拒否が出発点に位置づけられた。
「階級構成」概念が重要だったのは「階級意識」というマルクス主義の発想と訣別するためでもあった。「階級意識」という形而上学的で理念主義的なこの実体はマルクス主義の伝統のなかで中心的な役割を果たしてきたものであり、「即自的階級」から「対自的階級」への客観的かつ決定論的な移行において媒介の役割を果たすと位置づけられてきたものだ。技術的構成/政治的構成は即自的階級/対自的階級の言い換えではまるでない。ぼくの本では、階級意識概念を極限まで押し進めながらもこの概念の外に出ることのできなかったルカーチを取り上げ、オペライズモと対置させて論じた。1950年代のイタリアでは、革命闘争や社会変革はもはや労働者階級を通じてはなされ得ない、労働者階級はシステムに完全に吸収されてしまったという考えが広まりつつあった。54年にフィアットの工場で行われた内部選挙ではCGIL(イタリア労働総同盟)傘下の、したがって共産党傘下のFIOM(鉄鋼労働職員組合)が初めて負けることになり、これが共産党に方向転換を促すことになった。工場にはもはや何も期待できないとして共産党は中間層に向かうことになったのだ。イタリア国外においても、たとえばフランクフルト学派は西洋の労働者階級が機械内部に完全に取り込まれ、もはや消費することしか考えないようになったとし、労働者階級による革命的切断は不可能だと唱えるようになる。こうした文脈のなかで所謂「第三世界主義」がイタリアでも出現するが、そこで問題になっていたのは第三世界とされた国々での実際の闘争というよりも、革命への欲望を外部に投影するということであり、いまここにある力能ではなく、彼方に想像され空想された力能だった。
オペライスタたちが工場に見出したのは、したがって、意識的主体、自覚した主体ではなかった。マルクス主義の伝統では、この意識あるいは自覚によって政党や労組と労働者とが結びつくとされてきたが、そうした意識あるいは自覚が失われ、だからこそ、政党は労働者以外のもとへと向かうことになった。オペライスタたちが着目したのは、工場にやってきた新たな主体、イタリア南部からの移民だった。移民は、共産党や労組との関係のなかで十数年の経験をすでに積んでいるような従来の「職人労働者」とはまるきり異なる文化をその背景とする者たちで、御用組合に投票しさえする日和見主義者、ストライキのことも既存の労働運動のことも何も知ろうとはせず、まさに無自覚な主体だった。しかしオペライスタたちはそうした新たな労働者の出現に関心をもち、彼らとのコンリチェールカを組織し、彼らがどうしてストライキや労組運動に参加しないのかを理解しようとした。この活動を通じてオペライスタたちは、新たな労働者たちがストライキなど無意味であり、労働運動のアイデンティティの再確認でしかないと考えていること、だからこそまた、もっと具体的かつ物質的に物事を捉えている御用労組に投票し、できるだけ少なく働き、できるだけ多くの賃金を得たほうがよいと考えていることを発見するのだ。
オペライズモが登場してきた時期のイタリアには、したがって、二種類の労働者がいた。一方には、敗北を感じている労働者たち、すなわち、共産党や労組に属する従来の労働者階級がおり、労働を誇りしていたこれらの職人労働者たちは、生産ラインの導入によって工場が自動化され機械化され職人労働それ自体が解体されるなかで、その誇りの根拠をもはや見出せなくなっていた。そして他方には新たな主体、無自覚な主体がおり、彼らは労働運動に対して、また、労働文化あるいは工場文化に対して「外部性」をなし、この外部性を「拒否」として表現していた。
1962年7月、例年この時期に行われる労使交渉の際、UIL(イタリア労働連合)が他の労組との協調を破り単独でフィアットと合意してしまったことを契機として、UILの本部のあるトリーノの憲法広場を労働者たちが占拠し、警官隊と衝突、多数の逮捕者が出るという出来事が起こる。経営者たちが暴徒を雇ったのではないかとその当時まことしやかに言われたが、その理由はこの広場占拠が共産党の指導下でなされたものではなかったからだ。当時の左翼の考え方においては、意思決定はすべて共産党に委ねられるべきであり、労働者階級がいつ何をすべきかは共産党が決定するのであって、労働者階級の自律的発意といったものはあり得ないとされていた。憲法広場を埋め尽くし三日間にわたって大暴れした者たちについて警察が作成した報告書では、彼らは労働者にしては若すぎる、彼らの服装や行動様式から見ても彼らは労働者ではあり得ないとされた。興味深いのは、報告書の語っていることがまさに真実そのものだったという点だ。逆に言えば、報告書がまるきり理解していないのは、まさに、階級構成が変容したということだった。階級の技術的構成も政治的構成も変容していたのだ。テイラーシステムの導入された工場において機械は、労働力を新たな仕方で組織化し直しただけでなく、労働者の新たな主観性を産み出しもした。警察の報告書はそうした変容をまるきり理解していないのである。新たな行動様式が出現しつつあったのだ。この新たな行動様式をアルクァーティは労働者たちの「組織化された自発性」あるいは「目に見えない組織化」と呼んだ。要するに「自律性」のことだ。
ぼくの本の副題に含まれているもうひとつの概念、「主観性」概念は、階級構成という問題設定のその中心に位置するものだ。「主観性」はマルクス主義の考える歴史には登場し得ない概念だ。マルクス主義においては、主観性は階級意識の発展のその段階に応じて客観的に決定されるものだとされ、階級意識の発展それ自体は資本主義の発展のその段階に応じて決定されるとされるからだ。オペライスタたちが着目したのは新たな労働者の行動様式であり、その可能性だった。「大衆労働者」と名付けられたこの新たな労働者は当時、量として多数派をなしていたわけでもないし、資本主義のハイアラーキーのなかで中心的存在だったわけでもない。大衆労働者の中心性は政治的なものだった。そう言えるのは、彼らの新たな行動様式が潜在的に転覆的なもので、経営者たちに痛手を与えることのできる可能性を孕んでいたからだ。60年代の闘争は実際、まさにそうしたことの実現で、この闘争サイクルは大衆労働者という主体それ自身が止揚されるまで続いた。止揚も闘争のただなかでなされた。闘争はつねに、労働者としてのおのれの存在それ自体に抗する闘争でもあるからだ。闘争は「拒否」だが、拒否の対象は資本の下での労働だけではなく、労働力としての主体自身でもある。オペライズモはつねに「闘争の先行性」を唱えてきた。闘争がまずあり、闘争が発展過程を決定する。闘争があって初めてそれに対する資本のリアクションがあり、資本主義システムの再編成(技術的再編成、生産労働の再編成)がなされる。今日、ぼくたちはもはや60年代と同じ時代を生きてはおらず、新たな主体が登場しているが、それもまたそう長くは続かず、歴史はさらに先へと進むというわけだ。
どうして以上のような概念を今日、再び取り上げ直す必要があるのか。今日では「ポストオペライズモ」なるものが頻繁に語られている。しかし、この表現には、時系列的に見て何かの後にやってきたという理由から「ポスト〜」とされる類いのすべての表現に一様に孕まれている曖昧さと受動性とがやはり伴っている。アングロサクソン世界において新たな大学のモデルとして提唱されている所謂「グローバル・ユニヴァシティ」の定義としても「ポストオペライズモ」は語られているが、この例がよく示しているように、「ポストオペライズモ」という表現の使用にはオペライズモの理論をコンフリクトや階級構成、革命的主観性といったことから切り離そうとする傾向がある。しかし、コンフリクトや階級構成、革命的主観性から切り離されたオペライズモはもはやオペライズモとは何の関係もない。アングロサクソン系を中心に学者たちが自分の業績形成のために今日「イタリアン・セオリー」の名の下に試みているオペライズモ理論の「捕獲」は、まさに、この切り離しに存している。オペライズモ理論の捕獲はまさに本源的蓄積そのもの、共有の知の囲い込み、エンクロージャーだ。「この知は私のものだ、もし使用したいなら私にレントを支払え」と彼らは言うわけだ。
アングロサクソン世界で創り出された「ポストオペライズモ」という言葉を、ここイタリアでもぼくたちは、自分たちのものではないと知りながら、80年代以降の状況を表現する言葉として便宜上使うことになった。イタリアでは、70年代の闘争の敗北の後に出現した新たな労働過程を解釈しようという試みがなされ、そこで所謂「ポストフォーディズム」論が形成され、「非物質的労働」「認知労働」といった新たな労働概念が創り出された。これは正しい認識だったと言える。同時期には「ル・モンド・ディプロマティック」派が中心となって「単一思想」論が展開されてもいた。ネオリベラリズムの到来によって世界はもはやいかなる余白も残さないものとなり、フランシス・フクヤマのいう「歴史の終焉」に真に至ったといった議論だ。「ポストフォーディズム」論はこの議論に対し、歴史はけっして終焉しない、現に新たな労働形態や生産形態が出現しているではないかと異論を唱えたわけだ。しかし、この正しい前提から出発しながらも「ポストフォーディズム」論は階級構成の問題を再考しようとはしなかった、主観性の問題に取り組もうとはしなかったのだ。
今日の階級構成(技術的構成と政治的構成との関係)が50年代から60年代にかけてのそれと同じものではない、テイラーシステム型工場とフォーディズム社会とにおけるそれと同じものではないのは言うまでもない。「ポストフォーディズム」論の最大の問題は、技術的構成が直ちに政治的構成に転じるかのように議論を進めてしまう点にある。先に、オペライスタたちが大衆労働者を新たな形象として同定したとき、大衆労働者は資本主義のハイアラーキーにおいて中心的形象をなしていたわけではなく、大衆労働者の中心性は、その外在性が転覆的行動様式のポテンシャリティに結びついていることに存していたという話をした。技術的構成と政治的構成とが鏡像の関係をなすことはけっしてない。それらを鏡像として捉える考え方は「現実の社会主義」のなかで創り出されたものだ。1930年代のソ連では、工場における細胞リーダーは労働の組織化のなかでより技術的能力に長けた労働者が務める役職とされていた。これとは反対にオペライズモでは主観性が問題とされ、主観性こそが技術的構成/政治的構成の鏡像関係を破壊するとされたのだ。すなわち、主観性こそが政治的構成のとり得る方向を決定するのであり、主観性こそが技術的構成の切断の可能性を産み出し「再構成」への道を拓くということだ。ところが、たとえば「非物資的労働」論では、非物資的労働者が今日の資本主義のハイアラーキーにおいて中心をなしているとされるのと同時に、政治的構成においても中心をなしているとされてしまうのだ。これは間違っている。認知労働を語るのではなく、むしろ「労働の認知化」こそを語るべきなのだ。労働の認知化とは、資本蓄積についても、生きた労働の構成についても、知がそのハイアラーキーの形成において中心的な役割を果たすということを意味する。そうすることで初めて、階級構成を「ナレッジ・ワーカー」あるいは「クリエイティヴ・クラス」などと呼ばれる特定のセクターにおいてだけではなくその全体において問題にすることが可能となる。反対に、「非物質的労働」と呼ばれるもの(この表現それ自体がそもそも間違いだ。認知労働は非物質的ではなく、生きた労働に知が受肉することであり、労働はつねに物質的なものにとどまる)を階級の技術的構成の中心に位置づけ、この中心性をそっくりそのまま政治的構成のそれに翻訳してしまう議論では、労働者たちが物質的に表現している主観性が無視されている。階級闘争がなければ階級もないという考え方、主体が形成されるのはつねに闘争あるいは対立を通じてのことであるという考え方が放棄されている。ここで欠けているのは、新たな労働におけるその主観性の分析なのだ。
主観性の分析には注意が必要だ。80年代から90年代にかけてポストモダン思想の下では主観性はそれ自体でポジティヴな何か、美しい何か、自由な何かと考えられていたが、これは馬鹿げた議論だ。主観性はそれとしてはポジティヴなものでもネガティヴなものでもなく、ニュートラルなものでもない。主観性とはひとつの戦場なのであり、コンフリクトを通じて新たな何かが形成される場なのだ。敵対やコンフリクト、革命といった観点から主観性の問題に取り組む場合、主観性がその大部分において資本によって形成されているということ、資本によるこの主観性形成を切断するということがつねに問題になる。「非物質的労働」あるいは「認知労働」といった議論では「協働」の中心性というものが同時に問題にされるが、その協働はいったい誰のための協働なのか。資本のための協働にほかならない。協働に別の可能性を見出すためには、資本による主観性形成のその切断を問題にしなければならない。「対抗主観性」の形成プロセスを問題にしなければならないのだ。ポストオペライズモは、技術的構成/政治的構成の関係も再構成も問題にせず、主観性についてもそれを対抗主観性形成の観点からは問題にしないため、議論が抽象性の次元にとどまり、社会的過程の物質性が把握されないままに残されてしまうのだ。
ぼくの本は、ひとつの理論サイクルとしての以上のような「ポストオペライズモ」論のその理論的有効期限の満了を宣言するものだ。オペライスタたちがマルクス主義に抗してマルクスから出発したのだとすれば、今日、我々は、ポストオペライズモに抗してとまでは言わないにしても、しかしオペライズモから再出発し、ポストオペライズモとは別の方向に向わなければならない。すなわち、階級構成と主観性という問題に対峙し直すという方向だ。その際にはまた、同時に、「政治領域の自律性」というよりいっそう問題の多い路線とも闘わなければならない。制度的過程を「上から」捉えようとする「政治領域の自律性」論は、オペライズモがつねに把握し得てきたものを見失い、曖昧なものにしてしまう。主観的行動様式の表現のその両義性のただなかに身をおき、そこでの傾向を理解するという作業を再開しなければならないのだ。
この本は何に異論を唱えているのか。何に抗して書かれているのか。言うまでもなく、多くのものに抗して書かれている。何よりもまず、資本に抗して。敵対的主観性、ミリタント的主観性はつねに資本に抗して生じるものだ。この意味で、いかなる敵対性ももはやないと喧伝するポストモダン思想、所謂「弱い思考」もまたこの本の敵だ。ぼくたちがミリタントになるのはこの世界に対して憎悪を抱いているからであり、この憎悪を出発点とすることで初めてぼくたちは生産へと身を投じ、この世界を破壊し新たな世界を構築することへと向うのである。したがって、鍵となるのはつねに「拒否」だ。自分がいまおかれている条件を拒否し、それを変革し転覆することへと、そして、新たな条件を構築することへと向う。ぼくの本が異論を唱えているのは、また、ポストオペライズモの無規定な抽象性に対してでもある。ポストオペライズモは、今日、既存左派のシンクタンクとして名乗りを上げ、様々な「提案」をするようになってきている。60年代に労働者がその闘争で行ったのは「提案」などでは断じてなかった。彼らが行ったのは「拒否」だ。労働を拒否し、自分自身の条件を拒否した。「できるだけ少なく働き、できるだけ多くの賃金を得る」とは「提案」などではまるでない。経営者が10をよこしたら、100を要求し、100をよこしたら、1000を要求するということなのだ。「市民所得」(ベイシック・インカム)をめぐる今日の議論についても同様だ。ポストオペライズモには、資本家たちに対して、市民所得は彼らにとっても好都合だと説明しようとする傾向があるが、もし資本家たちに好都合なら、我々にとって好都合なわけがない。ここで蔑ろにされているのは主観的行動様式だ。市民所得においては誰が主体なのか。ぼくにとっての関心事は、階級主体が市民所得をいかにおのれのものにするかということであって、「提案」としての市民所得などではない。市民所得が「提案」になってしまった瞬間から、市民所得が革命的切断の道具となるための空間は閉じられてしまう。力関係が見失われてしまう。富の再分配は合理性といったタームでは説明できない。主体たちが資本家を脅かすということが必要不可欠なのだ。脅かされてもいないのに、どうして資本家たちが富を再分配したりすることがあろうか。構築を通じてこそ初めて富の再分配はなされる。「提案」の次元に身をおく限り、そうした力関係の次元、闘争の先行性は見失われたままにとどまるほかない。今回の本は、マキャヴェッリの言うような意味での「君主」たちの生産を新たなコンテクストのなかにおき直すものだ。ぼくの本それ自体が、君主たちを生産するのではない。それをなすのはまさにミリタントであり、彼らこそがコンリチェールカを通じて、階級の技術的構成や政治的構成、主観性や対抗主観性といった問題を実践的に解決するのである。
「ミリタンシー」「ミリタント」という概念をその強い意味で復活させなければならない。「ミリタント」という言葉はアングロサクソン系の「アクティヴィスト」という言葉が流行するなかで、忘れられたとまでは言わないまでも、少なくとも、それを口にするのが恥ずかしいものとなってしまった。今日では「ミリタント」はトロツキー主義やマルクス=レーニン主義といった古い構造に属するものと理解されるようになり、それに対して「アクティヴィスト」はより現代的な何かと理解されている。アクティヴィストとは原発といったようなひとつの問題に取り組む者のことであり、その問題が解決すれば、アクティヴィスト自身もアクティヴィストであることをやめる。これに対してミリタントとは革命を遂行しようとする者のこと、敵を破壊しようとする者のことであり、「ヴォランティア」などと同一視され得るようなものではまるでない。ミリタントは階級構成から離れては存在せず、階級構成を創り出す。ミリタントはいわば聖パウロのような形象であり、この世界に生きながらこの世界に属しておらず、階級構成のただなかに身をおきながら、その内部において階級構成に抗う。ミリタントとは、定義上、全面的に命を賭して闘う者のことだ。ミリタントとは何かという問題を再考することは、ミリタントであることを出発点として物質性を再考することなのだ。ぼくたちは今日、上昇局面と下降局面とを繰り返す一種の循環気質(躁鬱)に揺れ動く時代を生きている。躁状態と鬱状態とを繰り返す金融市場の循環気質だが、同じような循環気質はミリタントの世界でも生きられている。しかし、闘争の下降局面、闘争不在の局面が他の局面よりも重要でないとは、ぼくは思わない。それどころか、他のどんな局面よりもずっと重要なのだ。闘争が存在するときにはミリタントはそれに遅れて到来するが、闘争が不在であるときには、どうしたら闘争が出現するかを理解しなければならず、そこにミリタントの責務があるからだ。90年代末に行われたインタヴューでロマーノ・アルクァーティは、62年の憲法広場での出来事について「あなたたちオペライスタは闘争のあのような勃発を予測していたか」と尋ねられたの対し、「私たちは予想していたのではなく、それを組織したのだ」と答えている。まさにここにこそ、階級闘争とミリタントの存在とについての真理のすべてがあるとぼくは思う。客観的かつ決定論的な階級意識という発想はここには微塵もない。党が絶対的な権力を持ち、次の階級闘争を決定するといった馬鹿げた考えはここには微塵もない。しかし同時にまた「自発性主義」的な発想もここにはない。ミリタントが赴くのは可能性、ポテンシャリティがあるはずの場所であり、そこでミリタントはまだポテンシャリティでしかないものを読むのであって、すでに存在するものを読むのではない。ミリタントはすでに存在しているもののもとへと赴くのではなく、存在へと転じる可能性のあるもののもとへと赴くのだ。この能力こそをぼくたちは身につけなければならない。とりわけ、闘争が出現していない局面においてミリタントに必要なのは何よりもこの能力なのだ。
(第二部に続く)